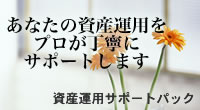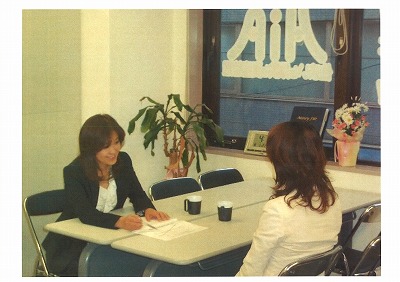|
(2) 税金コストを抑える |
|
リターン向上のための戦略 その2
税金コストを抑える
年1%以上の(実質的な)リターン向上効果を狙います。
投資対象により、また投資の時期により
さまざまな形で課税が行われます。
それらの税金は無視することができない
大きなコストとなる場合があります。
資産運用に関わる税金の種類には
どのようなものがあるでしょうか。
投資の時点別に整理してみました。
〜 運用開始時 〜
最初に支払うことになる税金ですね。
運用を開始するとき
投資商品を購入するために、購入手数料がかかります。
この手数料には消費税がかかります。
投資金額の1〜3%に当たる手数料に対して
消費税が5%かかるわけです。
税額は、購入金額全体の0.05%〜0.15%程度に
なるでしょう。
100万円の投資なら、手数料が1〜3万円
その消費税が 500円〜1500円
これは、ほとんど気にする必要のない税金コストです。
〜 運用期間中 〜
運用している期間中にも税金はかかります。
運用中に発生するインカムゲインに対する税金です。
税率はインカムゲインの種類によって以下のようになります。
| 預金・債券: |
利息にかかる税金(原則20%) |
| 投資信託: |
分配金にかかる税金(原則20%) |
| 株式: |
配当金にかかる税金 (原則20%) |
ちなみに、平成24現在の上場株式の特例はこちら
| 配当の支払時期 |
源泉徴収税率 |
(税率内訳) |
| 所得税 |
住民税 |
| 平成21〜25年末 |
10% |
7% |
3% |
| 平成26年以降 |
20% |
15% |
5% |
|
|
いわゆるインカムゲイン(定常的な収入)からは、
20%の税金が引かれるのが原則です。
例えば、年間の純粋なインカムゲインが5%あれば、
そのうちの1%は税金として引かれることになります。
つまり
100万円の投資なら、 5%のインカムゲインは5万円
税額は 5万円 x 20% = 1万円
投資額の1%に相当しますね。
残りの4%にあたる4万円は
再投資により複利で運用されることになります。
そう考えると、引かれる1万円は
複利効果の減少も考慮すると
決して無視できないコストであるといえます。
手取りのリターンを最大にするためには
できるだけインカムゲインが生じない
仕組みの金融商品を選ぶことをおすすめします。
インカムゲインが生じないということは
その分、キャピタルゲインが増えるということです。
具体的に、税金面で有利なカテゴリーを挙げてみましょう。
長期の債券による運用なら
× 利付き債券
○ ゼロクーポン債
△ 低クーポン債
○ ドル建て個人年金
短期の債券による運用なら
× 外貨預金
○ 外国為替証拠金取引 ※1〜5倍のレバレッジで使用しましょう
(ただし、決済するまで金利を含み益のまま持ち越せるもの)
投資信託なら
× 毎月分配型ファンド、分配金のあるファンド
○ 分配金を出さない方針のファンド
○ 比較的コストが低めの投資型年金
株式なら (業績が順調であることを前提とすれば)
× 配当が高い株式
○ 配当が少ない(もしくは無配の)株式
〜 運用終了時 〜
運用終了時にかかる税金には、何があるでしょうか。
以下の3つの税金について、おさえておきましょう。
1. 譲渡所得
標準として覚えておきたいのは、譲渡所得です。
株式や投資信託の売却時には、
純粋に儲かったお金に対して
譲渡所得として原則20%
(今は期間限定10%)の分離課税がされます。
2. 雑所得
一般のサラリーマンが
まとまった利益(年間20万円以上)を出すと
少し不利になるのが雑所得 です。
雑所得は、「総合課税」という扱いになります。
以下の所得は雑所得になります。
● 外貨預金における為替差益相当額
● FX(外国為替証拠金取引)による利益
● 保険会社の金融商品(ドル建て個人年金、投資型年金など) において
年金受取を選択した場合の、毎年の純益相当額
たとえば
年収600万円くらいのサラリーマンの場合
およそ30% (=所得税20%+住民税10%)の
実質税率になるケースが高いでしょう。
収入のある時期に受け取ると不利になる可能性があります。
ただし
老後などの所得が少ないタイミングで受取れば、
15%以下の実質税率になるでしょう。
その場合は、譲渡所得と比べても不利とは言えません。
3. 一時所得
実は、3つの中で最も有利なのが一時所得です。
一時所得も「総合課税」となります。
ただし、所得の計算が有利になっています。
一時所得の計算は、以下のとおりです。
収入 − 50万円 x 1/ 2
純益相当額から50万円を差し引いて、さらにその半分
課税は、一時所得金額を総所得に合算です。
お得になりそうですね。
対象となる所得にはどのようなものがあるでしょう。
●保険会社の金融商品で、
ドル建て個人年金
投資型年金
などの満期一括受取り ・ 一部解約における純益相当額
が、一時所得の扱いとなります。
例えば、投資型年金でファンドを上手にスイッチングして
10年後に150万円近くの利益が出たとしたら、
3年間に分けて解約するの方法も検討の余地があります。
|
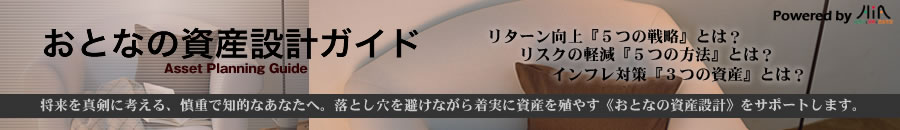
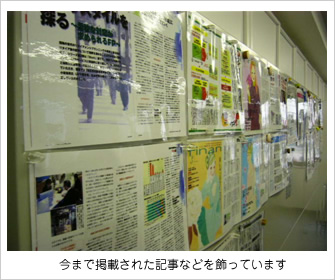 →FPの事務所風景はこちらから
→FPの事務所風景はこちらから