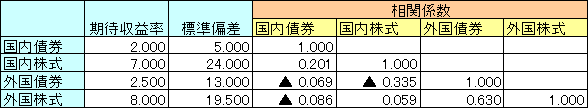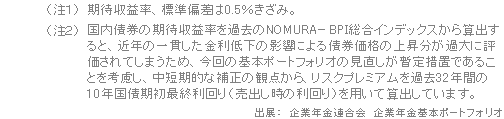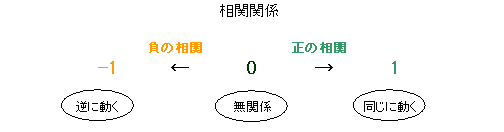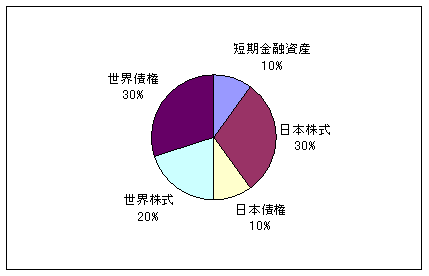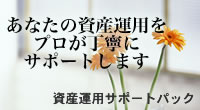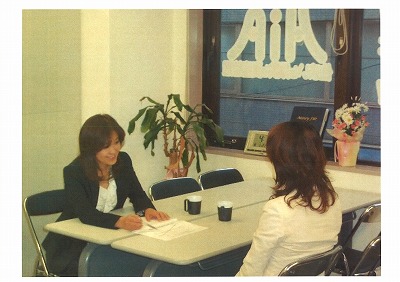|
3 資産クラスの分散 |
|
- リスク軽減のための5つの方法 その3 -
〜 資産クラスの分散 〜
「資産運用でポートフォリオ全体のリスクを軽減するために、
大切なことはなんでしょう?」
という質問をAさんとBさんにしてみました。
Aさんは、
「できるだけ多くの銘柄や、多くの金融商品に投資をすれば、
リスクが減りますよ。徹底的に分散することです。
例えば、日本の上場株式を全銘柄買うとか・・・」
Bさんは、
「株式と債券と不動産など、
お互いに『相関性』が低い銘柄や
金融商品に投資をすれば、
すべてが同時に下落する確率が低く
なるので、ポートフォリオ全体のリスクが減りますよ」
Aさんの発言は、1銘柄の分散のことですね。
多くの株式に分散投資をしようとすると、巨額のお金が必要になりますが、
ETFによって比較的少額で上場銘柄をまとめ買いする方法もあります。
しかしここでは、Bさんの発言のように、
様々な種類の金融資産(=資産クラス)に
分散してリスクを軽減する方法を見ていきます。
同じような動きをするのか、違う動きをするのかを計る指標
として使われるのが「相関係数」(ソウカン・ケイスウ)
という指標です。
相関係数は1から−1までの数字を取ります。
1に近ければ同じような動きをして「相関性が高い」といいます。
−1に近ければ完全に逆の動きをして「相関性が低い」といいます。
つまり、相関係数ができるだけ−1に近いもの
(1よりは0.5、0.5よりは0、0よりは−0.5…など)
に投資をすることによって、少ない銘柄数の投資でも効果的な
リスクの軽減ができるのです。
例えば、日本と世界の株式と債券の相関関係は
以下のように現されます。
国内株式と外国債券の相関係数はマイナス0.335ですから、
2つの資産の動きにはあまり関係性がないと言えそうですね。
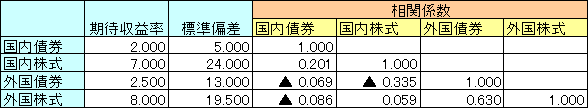
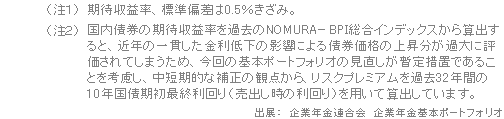
相関関係の数値の意味は、下の図を参考にしてください。
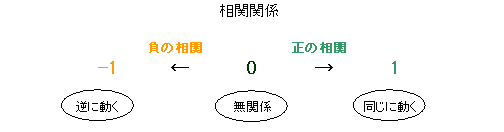
さて、資産の配分を決定することを、
「アセットアロケーション」と呼びます。
資産運用の成否を分けるのは、この
アセットアロケーションにあるといっても過言ではありません。
銘柄を選ぶ前に、まずはご自身の資産のために
相関性を考慮したアセットアロケーションを作ってみましょう。
以下は、国内と海外に資産を50%ずつ配分し、
株式の比率を高め(50%)にしたアセットアロケーションの一例です。
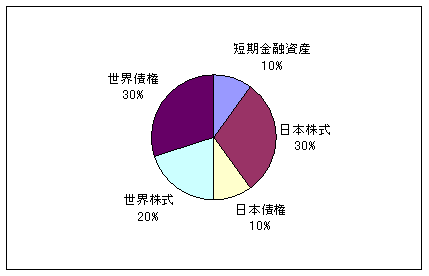
|
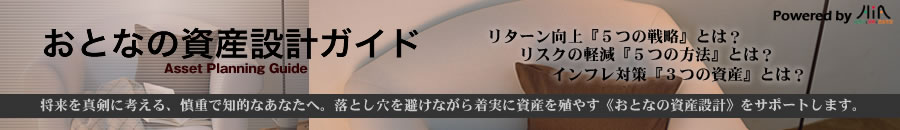
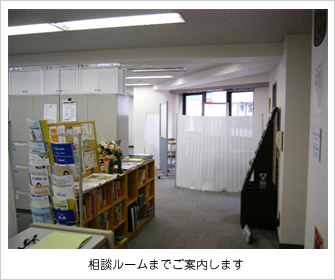 →FPの事務所風景はこちらから
→FPの事務所風景はこちらから